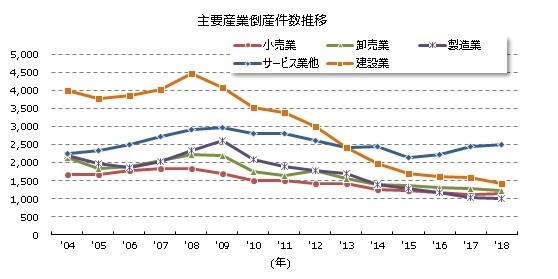私はオープンソースを事業の中心に据える会社に勤めてもう10年以上になる。転職した当時は、ビジネスの世界ではまだメインを張れるほどメジャーではなかった。転職前の会社は日本法人が2万人以上いる外資系の巨大IT企業に勤めていたので、「お前、ノーアウト満塁、ノーストライクスリーボールなのに、何でそんな難しい球を打ちにいくんだ!」とか、「LINUXがどんなに優れていたって、証券取引所のシステムで使われることは絶対にないんだぞ!」とか、散々言われたが、今やオープンソースはソフトウェア産業の中心にあり、東京証券取引所もニューヨーク証券取引所のシステムもLINUXの上で稼働している。別に私も確信があったわけではもちろんないが、パンパンと手を叩き、目をつぶって将来に思いを馳せたら、「これからはオープンソースだな」という信仰に近い啓示があり、「時間の問題ではあるが、その時計の針を早めるために、この会社に入るのは面白いかもしれない」と思って今の会社に転職をし、大変な思いをしながらも、なかなか今まで楽しく仕事をさせて頂いている。
前置きが長くなったが、何故こんなにくどくどと私の転職の話をしたのかというと『WHY BLOCK CHAIN』の筆者坪井氏が本書で未来を語る様が、私がオープンソースに転職当時の思いと重なるように感じたからだ。暑苦しく大げさな言葉を使うことなく、坪井氏は淡々した言葉でブロックチェーンの切り拓く未来への自分の考えを語る。流行りの技術を仰々しい言葉で語る人は多いが、彼の下記の冷めた言葉使いからは逆に凄みがにじみ出ている。彼の思いを読んだ時に、「あぁ、この人は信仰に近いような思いでブロックチェーンの未来を信じているだな」と感じた。
自分が世界を変えるんだ、とは思っていませんし、実際そんな力はありません。世界を変えるのは私ではなくブロックチェーンです。しかも、私が好むと好まざるとに関わらず、ブロックチェーンが必然的に世界を変えていく。私がやっているのは、ブロックチェーンのこの作用を察知して、変わっていく世界に合致した新しいビジネスを提案したり、自ら組み立てたりすることです。
『WHY BLOCK CHAIN』 第4章ブロックチェーンが拓く未来 P.166
正直、私は仮想通貨とブロックチェーンの関係がしばらく前までよくわかっていなかったし、ブロックチェーンが仮想通貨の要素技術であるとわかった後も、ブロックチェーンは仮想通貨のためだけにあると勘違いをしていた。本書は、ブロックチェーンをビットコインなどの仮想通貨と切り離し、IoT、5G、AIなどと並び次世代を切り拓く中核技術として、仮想通貨以外へのブロックチェーンの展開の可能性を語っている。コンセンサスアルゴリズムや分散型台帳などのブロックチェーンの中核技術も平易な言葉で説明されており大変わかりやすいし、単に礼賛するだけでなく、展開が見込める領域とその特性故に展開が見込まれない領域についても、冷静な視点で分析をしている点でとても好感が持てる。
一方でブロックチェーンは、「誰も管理していないのに自律的に機能するネットワーク」を実現します。GAFAのあり方を中央集権型のネットワークとすれば、ブロックチェーンは分散型、または非中央集権型のネットワークであり、大きく異る世界観です。ブロックチェーンは本質的に、GAFAのような大プレーヤーによる支配の構造を 崩していく作用を持っているのです。
『WHY BLOCK CHAIN』 序章 ブロックチェーンの今 P.17
私が本書を読んで、何より「ブロックチェーンは目が離せないなぁ」と思ったのは、中央集権型から分散型への流れを促進する要素技術であるという点だ。最近、四種の神器と言われている要素技術の中でその特性を備えるのはブロックチェーンだけだ。筆者は現在の中央集権型の法体系、規制とブロックチェーンの相性はあまりよくないので、着実ではありつつも変化はゆっくりと進行していくとまとめる。しばらく、英語の本を読んでいないが、おそらく少し進んでいるであろうアメリカの本でも読んでみようか、という気になった。